会社員のもぶ汰さんは、中間管理職としての日々の業務に追われていました。
リーダーシップとマネジメントスキルを鍛えることは、彼の上司たちから絶えず期待されていましたが、日々の業務が忙しくて学ぶ時間を見つけるのが難しい状況でした。
そんな彼にとって、求められていたスキル向上の手がかりはまだ遠くに見えていました。
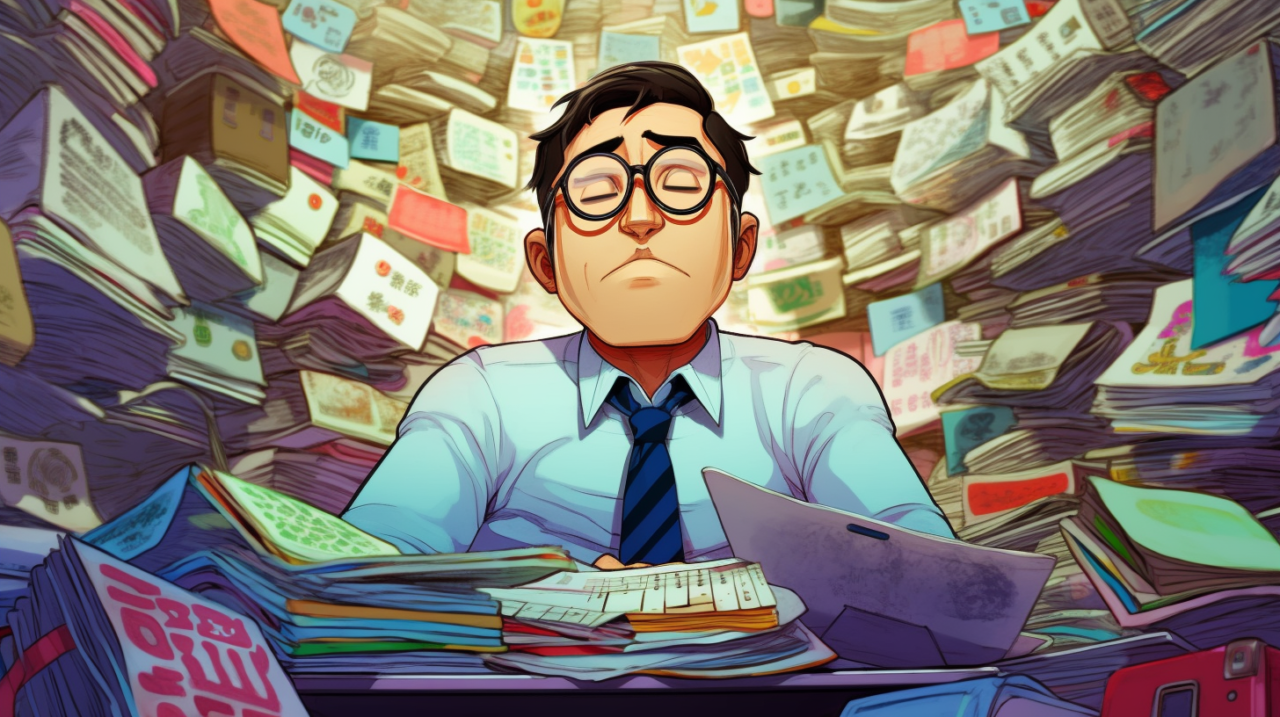
ある晩、もぶ汰さんはたぬきの幽霊、たぬゑもんと再度出会いました。
たぬゑもんは、もぶ汰さんが以前に出会ったことのある幽霊で、築き上げた長い経験から、様々な経営者を見てきていました。
そのため、彼はリーダーシップとマネジメントに関する多くの知識と経験を蓄えていました。
「もぶ汰さん、時間を見つけられないのなら、それを探しに行かなければならない。リーダーシップとマネジメントスキルを磨くためには、自分自身でチャンスをつかむ姿勢が必要ですよ。」

たぬゑもんは過去の経営者の例を引き合いに出し、彼らがどのように自分たちのスキルを磨いたのか、その具体的な手法をもぶ汰さんに説明しました。
「ビル・ゲイツは、毎年2回『Think Week』という一週間の読書休暇を取っています。この期間中、彼は新しいアイディアや技術に関する書籍や論文を読み漁り、新しい知識を吸収します。
自己啓発に時間を投資することで、彼は経営力を飛躍的に向上させることができましたよ。」

「また他の経営者は、毎日の業務の中で起こる問題を記録し、それらを解決するための戦略を考えていました。
問題が発生したときには、自分自身で解決策を見つける努力をし、それが新たなスキルを身に着けるきっかけになりました。」
もぶ汰さんはたぬゑもんの話を聞きながら、自分自身に問いかけました。
「僕も彼らのように新たなスキルを獲得することができるだろうか?」と。
しかし、彼はまだ自分の能力に自信を持つことができませんでした。
「もぶ汰さん、あなたが自分自身を信じなければ、誰もあなたを信じてはくれませんよ。あなたが新たなスキルを獲得するためには、まず自分自身に自信をもつことが重要です。”」

リーダーシップとマネジメントスキル
「ところで、もぶ汰さん。リーダーに必要な、リーダーシップとマネジメントについては理解している?」
もぶ汰さんは自信なく俯きました。
「リーダーシップは、方向性を示し、チームのモチベーションを高める役割を果たします。一方、マネジメントスキルは、具体的なタスクやプロジェクトを効果的に管理し、組織の目標を達成するための手段を提供します。」
☆リーダーシップ
特徴:
ビジョンの構築とインスピレーションの提供。個々のメンバーやチーム全体の能力を引き出す。
目的:
方向を示し、インスピレーションを与えることでチームを導く。
☆マネジメントスキル
特徴:
計画立案、組織、調整、監督、評価など、具体的なタスクの管理。
目的:
目標を達成するための具体的な手法やプロセスを提供する。
{おススメサイト:リーダーシップとマネジメントの違いとは?ドラッカー流リーダーシップの定義や特徴・スキルアップの方法を解説}

リーダーシップスタイル
「一口にリーダーシップといっても、実は様々なスタイルが存在するの。
色んな環境下で、適したスタイルがあるから、どれが一番いいリーダーなのかは断言できないけど、自分に合うスタイルは存在するわ。」
リーダーシップスタイルの種類と概要:
指示型リーダーシップ (Autocratic Leadership):
概要:
リーダーが全ての決定を行い、部下に指示を出すスタイル。
適用:
短期的な決定や緊急時に有効。
参加型リーダーシップ (Democratic Leadership):
概要:
チームメンバーの意見やフィードバックを取り入れて決定を行うスタイル。
適用:
チームのモチベーションを高め、クリエイティブなアイディアを求める場面。
変革型リーダーシップ (Transformational Leadership):
概要:
ビジョンや目標を共有し、チームを変革や成長に導くスタイル。
適用:
組織の変革や新しい方向性を求める場面。
取引型リーダーシップ (Transactional Leadership):
概要:
報酬や罰を用いて、期待される業績を達成させるスタイル。
適用:
明確な目標が設定され、その達成を求める場面。
放任型リーダーシップ (Laissez-Faire Leadership):
概要:
チームメンバーに自由を与え、自らの判断で行動することを奨励するスタイル。
適用:
経験豊富で自律的なチームメンバーがいる場面。

影響力の源泉
「もぶ汰さんは、『今日からこの人がリーダーです。』っていきなり知らない人の下に付くのは嫌じゃないかな?
リーダーがリーダーたる所以がないと、この人に付いて行こうとは思わないよね。
リーダーの影響力の源泉はどんなものがあるのかも、知っておくといいよ。」
影響力の源泉
専門知識:
リーダーが持つ専門的な知識や経験。
カリスマ性:
リーダーの魅力や説得力。
ポジション:
リーダーの組織内での地位や役職。
報酬と罰:
チームメンバーへの報酬や罰をコントロールする能力。
関係性:
チームメンバーとの信頼関係や絆。
ビジョンと目標:
明確なビジョンや目標を持ち、それを共有する能力。
「The Bases of Social Power」は、John R. P. French Jr. と Bertram Raven によって1959年に発表された論文で、社会的な影響力の源泉に関する理論を提案しています。
制勢力 (Coercive Power):
他者に罰を与える能力、または他者から望ましいものを取り除く能力に基づく勢力。
報酬勢力 (Reward Power):
他者に報酬を提供する能力に基づく勢力。
正当勢力 (Legitimate Power):
役職や地位に基づく勢力。特定の役職や地位を持つことで、他者に対して何らかの行動を要求する権利があると認識される。
専門勢力 (Expert Power):
特定の知識やスキルに基づく勢力。他者がその知識やスキルを尊重し、それに従うことを選ぶ。
準拠勢力 (Referent Power):
他者との関係性やカリスマ性に基づく勢力。他者がリーダーを尊敬し、そのリーダーと同じようになりたいと願うことから生じる。
後の研究で、以下の勢力が追加されました。
情報勢力 (Informational Power):
特定の情報を持っていることに基づく勢力。

リーダーのマインドセット
もぶ汰さんはリーダーが持つべき〈心の持ちよう〉があるのか尋ねました。
「リーダーのマインドセットは、困難を乗り越え、組織を成功に導くために必要なものです。
例えば、常に成長するマインドセットを持つ経営者であれば、自己の知識とスキルを継続的に向上させ、新たな挑戦に対応することができます。 」
マインドセット
・常に成長するマインドセットを持つ
・失敗から学ぶマインドセットを持つ
・開放的なマインドセットを持つ
・長期的な視点を持つマインドセットを持つ
・社会貢献を志向するマインドセットを持つ

マネジメントスキル
「マネジメントスキルで身に着けるべき要素は5つ。リーダーシップを整えつつ、ぜひとも身に着けてもらいたい能力だよ。」
コミュニケーション能力:
組織内のコミュニケーションを円滑にするための能力。部下や上司とのコミュニケーションを密にし、情報や意思決定を円滑に伝えることが重要。
チームビルディングスキル:
チームの結束を強化し、メンバーのスキルや能力を最大限に引き出す能力。信頼関係の構築や、共通の目標に向かっての協力が求められる。
問題解決能力:
複雑な状況や課題に直面した際の、冷静な判断力と分析能力。包括的な情報収集と適切な解決策の選択が必要。
柔軟性と適応能力:
瞬時に変わる状況や環境に対応する能力。自身のスケジュールや優先順位を柔軟に調整し、効果的なマネジメントを行う。
リーダーシップスキル:
組織やプロジェクトのビジョンを明確にし、メンバーを指導・サポートする能力。リーダーシップの資質を身につけ、チームの成功に貢献する。

もぶ汰さんは自分自身の時間を作り、その時間を使ってリーダーシップやマネジメントに関する書籍を読み始めました。そして、自分の仕事で起こる問題を解決するための新たな方法を探すため、毎日の業務を通じて学ぶことを心がけました。
“時間がないと言う代わりに、時間を作る。自分自身の成長を優先する。これが、真のリーダーシップとマネジメントスキルを身に着けるための秘訣”
なのだと、もぶ汰さんは学びました。
「自分自身のリーダーシップとマネジメントスキルを磨くためには、自分自身の成長を優先することが大切だよ」
と最後にたぬゑもんは伝えました。

トリビア 「CEO効果」の神話
企業の成功は、一般的にはCEOのリーダーシップに大きく依存していると考えられがちですが、実際には会社の文化やチームワーク、市場環境など、CEOの影響力を超える要素が数多く存在します。
カリスマ的なリーダーよりも実績を積んだリーダーの方が、長期的には企業に良い影響を与えることが多いと言われています。しかし、実は多くの人はカリスマに惹かれやすいため、短期的な魅力に目がくらみがちです。

『経営』に関するおススメ書籍
DX時代の成功事例がゼロからわかる! 使えるビジネスモデル見るだけノート
そのビジネス課題、最新の経済学で「すでに解決」しています。 仕事の「直感」「場当たり的」「劣化コピー」「根性論」を終わらせる
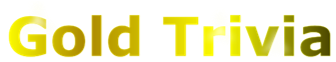




コメント